第3話「七つの罪」
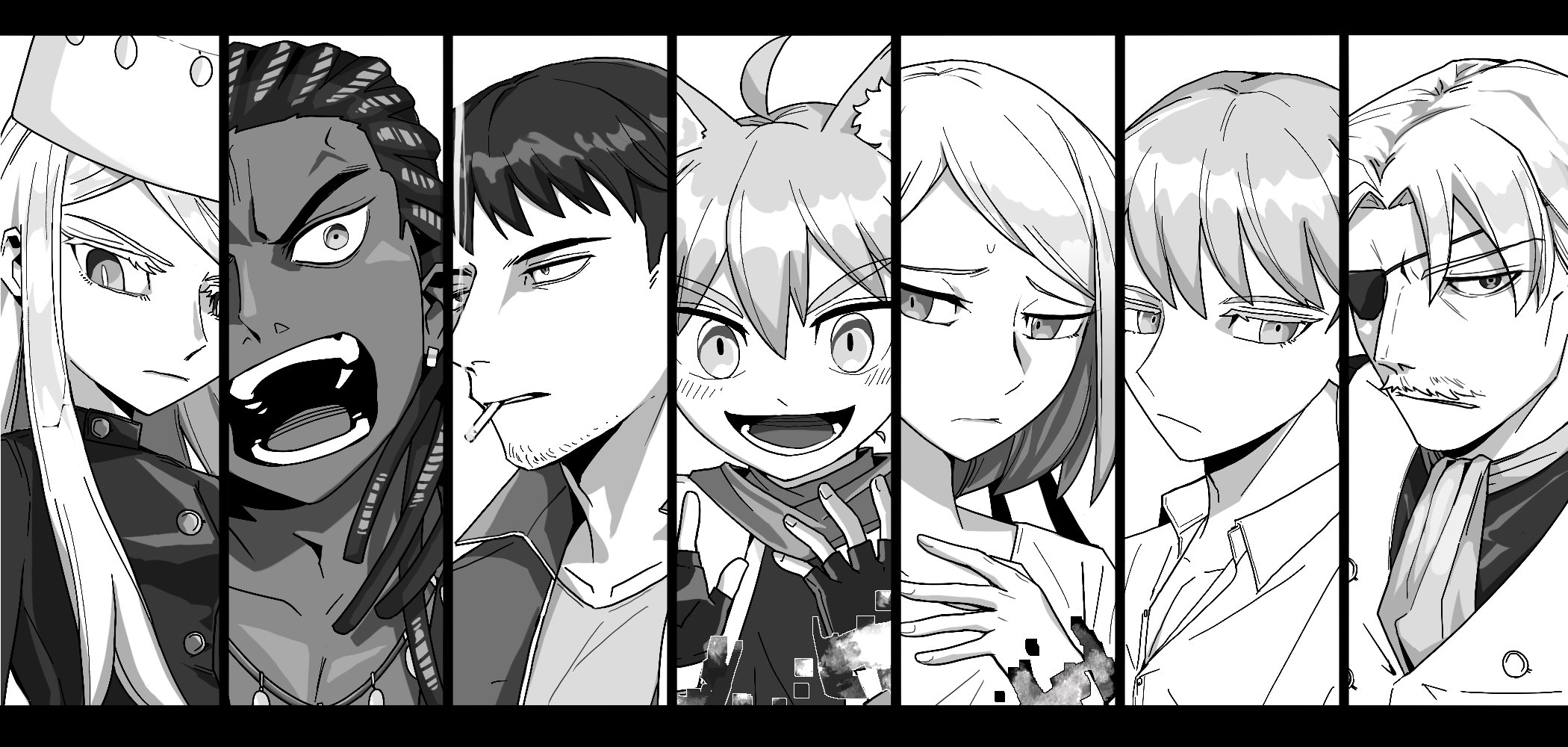
寝転がったまま、ロビンはぼーっと天井を見ていた。
(天国か、ここ……)
日差しが照っている。いや、果たして日であるのかも分からない。
空は白い。雲に覆われているわけではない。壁にしては開放感がある。この世ならざる風景。
体を伸ばすため腕を広げる。
「うん?」
腕を、肩幅より外に広げることができない。
青い枷。これが、手足の動きを封じていた。
足も同様に肩幅程度開くことはできるが、それでも枷は枷。
鍵穴はない。手首にぴったりフィットしていて、小細工をする隙間はどこにもない。
(こりゃあ、天国じゃねえぞ……!)
ロビンはがば、と上半身を起こした。
――視界に、円が六つ存在した。
空間の中央を囲むように円は配置されている。
そこに、六人の"罪人"がいた。枷に囚われ、円の中に収監されている。
ロビンも足元を見る。自分も丸い円に囲まれている。
足先でちょいちょいとそれをつついてみる。円の上に透明な壁があるようだ。
ロビンは壁を叩く。奇妙な反響音と共に拳が跳ね返る。
「"掴め"!」
ロビンはスペルを口にした。
「ああ? "掴め"、"つーかーめ"、"掴め"って!」
黄金の手は現れなかった。
「ここじゃ、力は使えない」
ロビンは声の方向を向いた。右隣の円だ。
藍色の作業着を着た男。
だいたい三十代くらいの顔に見える。無精髭の三白眼で、無表情。
彼は煙草を左手で口にあてがう。枷のおかげで、だらりと右手も持ち上げられている。
「もう"皆"試した」
「あんたはこの状況、分かる?」
「いや、さっぱりだよ」
「捕まる理由に心当たりは?」
「…………全く。君は」
「おれはたくさんあるぞ!」
ロビンは勢いをつけ、器用に立ち上がる。
左隣には女がいた。
薄紫がかったセミロングの髪。そこから伸びた四本の髪の束。
赤みがかった細い目。
臙脂色のスカートの女が座り込み、自分の体を抱きしめている。顔色は真っ白だった。
彼女も目覚めたばかりかもしれない。ロビンと目が合い、驚く。
「あんたもここに来たばっかり?」
「は、はい」
「おれも! 名前は?」
「私は――」
女は何かを言った。ロビンはきょとんとしている。
「よく聞こえなかった!」
「私は――です!」
彼女が声を張っても、くっきりと名前の部分だけ切り取られてしまう。
「ここだと名前が聞こえないんだ」煙草の男が口を挟んだ。
「おれは――!」
ロビンは試しに名乗ってみる。
「聞こえないです」
「おれはボビン! これはどうだ?」
「聞こえるってことは、それは名前じゃないな。ボビンくん」
「お前ら、よく遊べるな」
ロビンの獣耳がぴくと動いた。その声は、女の左隣にいるすまし顔の青年だった。
端正な顔立ちの若者で、白いシャツの上から青緑色のベルトを無造作に巻いている。
気取っていない、自然に身についた爽やかさを香水のように纏っている。
「あんたはなんか知ってる?」
「知るかよ。今、途方に暮れてんだ」
彼は長いまつ毛を伏せた。
「さっき、あいつからも同じことを聞かれたぜ」
あいつ、と青年が視線を向けた先には、まるで正反対の男が立っている。
隆々とした筋肉を纏う大男。ドレッドヘアをひとまとめにした髪型。
トップスの胸元は開いていて、赤褐色の肌を堂々と見せる。
封じられた両腕をぶらんと下げて、彼は仁王立ちをしていた。釣りあがった太眉。
「アンタも分からん仲間?」
「てめえ、その通りだっ!!」
彼は丸い目をかっ開く。
「なんでそんなカッカしてんの?」
「俺あこうやってふん縛られるのが、何より大嫌いなんだよ!!」
「そりゃ一部の変態除いてみんな嫌いだ。おれも仲間だぞ!」
「仲間だあ? んなこと言ってるとホントに俺の"革命軍"に入れちまうぞっ!!」
"革命軍"という言葉は、どこかで聞き覚えがあった。だが、ロビンには思い出せない。
「いや、それはいい」
「キッパリ断んじゃねえっ!!」
ロビンはにやにやしたまま、このライオンを放置して隣に視線を移す。
漆黒のドレスを纏った少女だ。
銀飾りを縫い付けた帽子を頭上に頂く。月白の色をした長い髪と、くすむ灰色のヴェールがその表情を隠している。
彼女は宙に浮いていた。
その高度は、いちばんに長身のドレッド男をも見下ろせる位置にある。古びた服装も相まって、まるで亡霊のようだった。
「あんたすげーな。浮いてんぞ」
薄い青色の軌跡を描いて、その瞳がロビンを見る。
氷の視線。
(っ!)
鋭利な殺意。
「……」
ロビンは黙った。悪寒が、策なしで踏み込む相手ではないと警鐘を鳴らす。
黒ドレスは視線を外した。ロビンからは、そのヴェールのかかった横顔だけが見える。
(変なやつだな)
つつけばとんでもないものが隠れていそうで面白そうだが、今はその時ではない。さっさと黒ドレスの右隣を見た。
眼帯をつけた壮年男。
整った口髭。不自然な皺や汚れの失せたシャツ。同様の黒のスラックスと、よく磨かれた革靴。彼自身の秩序にそぐわないものを、徹底的に排除している。
腰にビリヤードグリーンのエプロンを巻いている。それは、趣味でひととき付けている、という風でもなく、鳥における翼のように、常時体の一部として装備されているような自然さがあった。彼は料理人かもしれない。
「オッサンはさあ、ここいる理由に見当つく?」
「……」
彼は、苛立ちのリズムを靴で奏でている。
こちらを見ようともしない。無視を決め込んでいた。
ロビンはとすんと尻餅をつき、その透明な壁にもたれかかった。話しかけた六人に共通する特徴は見出せない。
「おれ、死んだと思ったらここにいたんだよな」
「わ、私もです」「俺も。世界の損失だ」
美男子は平然と言った。
「死因は? もしかすると同じだぞ」
ドレッド男は吐き捨てた。
ロビンは記憶を再生する。落ちていく景色。
「斬首刑だよ。青い髪のやつにやられた」
「お揃いですね」
木霊する少女の声に、七つの視線が集う。
きらきらと、光が罪人の囲う円の中心に湧いていく。
漆黒の四肢が形成され、青い髪が靡く。それは毛髪の集合というより、どこか溶け合った焔のようにも見えた。
瞼の下から大きな瞳が現れる。白目を脇へ押しやったような、肥大した瞳だ。その中にはいくつもの光の粒が瞬いている。
彼女は宙に体を預けている。余分な力を感じさせないその姿は、どこか人形のようにも見えた。
間違いなく、彼女はロビンの首を切った張本人だ。
「あいつだ。皆もそう?」
六人とも返事はしなかった。その沈黙は肯定を意味している。
「皆様、お集まりいただきありがとうございます。先程のご無礼をお許しください」
「テメエ!! ここはどこだっ!?」
ドレッド男が問いを投げる。
「ここは『裁きの間』」
少女は平坦な声で告げた。
「俺はマジで死んだのか?」
美男子が聞く。
「死んでいません。肉体から魂を離しただけ。この会合が終われば、魂は肉体へ還しますのでもう暫くの辛抱を」
彼女の言いぶりは、まるで機械のアナウンスのようで取り付く島がない。
「何者だ」
これは、黒ドレスが問うた声だった。
それは低く、威厳を宿す。有無を言わさぬ命令に近い。
ここにいる全てに、熱を奪う吹雪が襲った――そんな錯覚を抱くほどに、芯まで凍る"威圧"。
「……」
正体不明は表情を変えずにいる。黒ドレスの吹雪さえその体をすり抜けてしまったようで、少女は動じることがない。捕えられた七人と、少女とで、存在している階層が違うような錯覚をする程に。
舞台中央で七人の視線を受けながら、彼女は答える。
青い髪の少女。首を切った少女。
「わたしはイノセンス。肉体を持たない観測者、また、マルアハがこの星に降りることを知っていた者」
どうしてあの怪物の名前が出る?
「あなた達はマルアハを倒す、その役目に選ばれたのです」
澄んだ声は、ぽつんと水滴を垂らしたように空間へ広がった。
驚愕、困惑、苛立ち。丸い目、息を飲む音、眉間の皺。
ロビンは噴き出す。
「あははは! なに馬鹿なコト言ってんだよっ!」
なにが役目だ。それはヒーローが持っているもので、大どろぼうのものじゃない。
それに、周りを見てみた。ここに英雄の適性のあるやつがいるのか?
「くだらん、早く戻せ。煮込み途中の料理がある」
強面の眼帯の声は地を這う。関係のないことに巻き込まれたと考え、業を煮やしている。
笑う者、怒る者、困惑する者……各々の反応をイノセンスは見つめる。
ふと、その腕をすうと持ち上げ、指をさした。
「!」
少女の指は首を絶つ凶器だ。皆鞭で叩かれた動物のように、大なり小なり身構える。
イノセンスはまず、紫髪の女にそれを向けた。彼女は後ずさる。
「"見て"」
「"暴け"、"怒れ"、"眠れ"、"差し出せ"、"忘れろ"」
「“掴め”」
最後、ロビンへ向けた指をすうと降ろす。
「あなた達は生命活動の中で、『アビリティ』という力に目覚めましたね」
「アビリティっていうんだな。これ」
冷えた肝を押しつぶし、呟く。
ロビンの力はあの黄金の手だった。掴みたいと思ったものを、大欲の赴くままに掴む力。
「地上でアビリティを使えるのは、ここに集った七人だけ。アビリティは、唯一マルアハに打ち勝つ可能性のある力なのです」
「んなバカな!」
美男子は即座に拒否する。
「笑い話を」
眼帯の男は吐き捨てた。
マルアハ――星に滅びをもたらす異生物。
人類は、マルアハに僅かな傷ひとつつけることもできなかった。星のあらゆる天才が集い、知恵を絞っても、技術を進化させても、それでもマルアハに敵うことはなかった。
ロビンだって知っている。歴史のお勉強だ。現在の終末のいきさつ、人類が負け続けであること。
「……」
だが、本当に?
『ヨーマン、あれ"盗める"と思うか?』
もしも、本当だとしたら?
「あなた達は人類で唯一、『ナナツミ』を得ました」
イノセンスは言った。
「これは、わたしが全人類に蒔いた『ゲンザイ』という種が実ったもの。『ナナツミ』は対マルアハを想定したもので、膨大な魔力の使用、アビリティの行使を可能にします」
「俺はナナツミなんて持ってねえ」
ドレッドは両手を見せびらかした。
「ナナツミは魂に結びつくもの。目に見えるものではありません」
「でも、どうして私たちに、ナナツミができたんですか……?」
この場の七人に、共通点は見出せない。戦いに長けている、という風でもない。
「『ゲンザイ』は、溢れる欲や大渦の感情によって育つ。"大罪"と判断し得る巨大なエネルギー、その持ち者が『ナナツミ』を得るのです」
「大罪ィ!?」
ドレッド男は真っ白の犬歯を露にする。
「……!」
紫髪は目を見開いた。
「ナナツミは、それぞれで性質や能力が違う。故に分類を七つに分けました」
「嫉妬」
揺れる紫髪。
「色欲」
すまし顔の色男。
「憤怒」
怒り抵う者。
「傲慢」
氷雪の亡霊。
「暴食」
隻眼の料理人。
「怠惰」
煙向こうの男。
「強欲」
獣耳の子ども。
その銘を魂へ刻み付けるように、告げた。
「これが、あなた達の名前。あなた達の力。この力を使って、どうか、七体のマルアハを壊してください」
七体のマルアハに、七人の罪人、七つの力。
「俺はやらねえ。んなヒマねえんだ!」
「私は違う……」
「…………」
「私の"行為"を、そう、定めるか」
イノセンスは罪人を見下ろすのみだ。
「俺の名前であるわけねえだろっ!! お前は何が目的だ? いや、何の役を、俺たちにやらせようとしてんだよ――」
「——マルアハの弱点はあるのか」
ドレッド男の叫びが雷鳴のごとく轟いた後に。
"怠惰"こと作業着の男は、三本目の煙草の、一口目の煙を吐き出して尋ねる。
すぐに二口目を肺で弄ぶ。その黒色の三白眼が、まっすぐにイノセンスへ向けられている。
これに少女は応答する。
「頭上に浮いた、光の輪です」
どくん、と音がした。
「頭上の」
彼は煙草を除けないまま繰り返した。口元を覆うようにして添えられた手が、表情の一片を隠している。
「ええ。あの輪がマルアハの動力源。破壊すれば、マルアハは機能を停止する」
「だけど、さすがに命の危機を感じりゃあ、やつらは"起きる"だろ? ヒトの住処をチームで八割潰した野郎に、七人ぽっちが敵うかよ」
"色欲"は吐き捨てた。
「他に弱点はないんだな」
「はい。光の輪を破壊しなければ、マルアハは必ず再生する」
"怠惰"は煙を吐いた。
そもそも、あの光の輪こそ、史上最も多くの人類を消し飛ばした凶器だった。
あれは超高濃度の魔力を吐き出し、周辺一帯を真っ白に染める。
文字通り、光輪が魔力を放出したあとは、何も残らない。
最悪の兵器。厄災の象徴。終末を招く凶星。
「あの輪っかって、なんて名前だ?」
ロビンは聞いた。
一体何の質問だと皆が思った。馬鹿馬鹿しいとも。
それは必要のあることなのか? 名のあるものではないだろうし、知る必要もない。
だが、それはロビンにとって必要不可欠なものだった。
「《アス・ポルタ》」
《お宝》に呼び名がなくてどうする?
「あれは、実体のあるものなのか?」
「はい」
ロビンは跳ねるように立つ。
「この手で掴めるものなのか?」
時限爆弾みたいだ。だくだくだくと、体の中から音がしている。
「もちろん」
ばん、とロビンの脳裏にあの薄青の空が広がった。
昼の空にあっても、存在感を放つ青色。太陽の光と己の魔力で、不思議な輝きを散らす王冠。未知の輝き。
「望むところだ」
直観。これは縁なんだ。あの丸い円。
神様のプレゼント? 神はそこまで信じちゃないが。「やれ」と崖から突き落とされた。ならば「望むところ」だった。そもそも愉快で仕方がないし、笑いが勝手に込み上げてくる。役目なんてハナからないし、運命なんてドラマチックだ。それより合うのは挑戦状か。
あれは掴めるものなのだ。盗めてしまうものだった。はるか強大で人が敵わぬ災厄の化け物の持ち物だろうが、そいつの唯一の弱点だろうが、地上で何億の命を消した最悪の終末兵器だろうが、星を滅ぼすものだとだとしても――
ずっと見上げていた。きれいだと思った。
欲しい、と思っていた。
「イノセンス!」
呼び声が轟く。真っ白な空間、六人の罪人と処刑人。
今度はロビンが少女を指さした。彼女の目を見据え、睨み、豪快に笑う。
黄金の輝きが双眸を燃やす。
「あいつはおれが盗んでやる」
だくだくだくとうるさいこれは、宝を盗れと囃し立てる、大どろぼうの心臓だった。
"嫉妬"は自分の聞き間違えかと思った。"色欲"はその馬鹿馬鹿しさに言葉を失う。"憤怒"は目を丸くして、大笑いした。
"傲慢"は子どもを一瞥し、"暴食"は冷笑する。
"怠惰"はここに来て、初めて表情を変えた。
「ついでに人類なんとかなったら、ここまで美味い話はねえだろ! あはははは!」
"強欲"は天を仰いで笑っている。
「…………協力に、感謝します」
イノセンスは黄色の獣を見下ろした。
温度のない目が、微かに、微かに細まった。
そして、会合は終わりを迎える。ふいに空間がぐらりと揺らめいた。
間髪入れずに『裁きの間』にひびが入る。
「あぶねえっ!」
"色欲"は飛び退いた。円を貫いて、その雷模様が侵入してきたからだ。
イノセンスは視線をロビンから外した。
「目覚めのときです」
『裁きの間』はその姿を保てず、崩れていく。ついには地面が割れる。
「おい! 落ちるぞ!!」
"憤怒"が叫ぶ。
「目を閉じ眠りなさい」
「起きるか寝るかどっちなんだよっ!」
"嫉妬"は早々に目を閉じた。この全てが夢であることを祈りながら。
"暴食"も瞼を下ろす。抗うことも時間の無駄だ。
空間を構成していたものが崩れて、地面の役割を果たしていたがれきが宙に浮く。
白色の構築物がはがれてしまえば、その下には闇が広がっている。
"色欲"は恐怖にかられ、すぐに目を瞑った。
「くそっ」
"憤怒"も観念し、不服ながらもイノセンスの言うことを聞いた。
"傲慢"は窓辺に腰かけるような姿勢で宙に浮いている。天に浮いていくがれきなど目に入っていないように。
彼女はイノセンスを見据えている。
言葉は不要であった。そこに、明確な敵意が宿っている。
「イノセンス」
"怠惰"は、短くなってしまった煙草を、携帯している吸い殻入れに入れた。
そして聞いた。
「やりたくない、と言ったらどうする」
与えられた役目について。
「いいえ。皆、定めから逃れることはできない」
彼女の姿は、またもや光に分解されていく。
“怠惰”とイノセンスの問答をよそに、ロビンの意識もどこか白に霞んでいった。まだ目を開けていたいのに! なんとかロビンは声を発する。
「お前と話したい時はどうすればいい!」
「……夢の中で、私の名前を呼んでください。夢は、魂に近い場所ですので」
光に還っていく中、残されていた少女の胸像がそう答えた。
ロビンが返事を返す前に重い瞼が落っこちる。そして、自分がどこかへ引っ張られるような、引力を感じた。どこに帰っていくのだろう?
自らの身をかき分けていく濁流の中で、最後に彼女の声が聞こえた。
「どうか、星をお救い下さい」
◇
体の痛みで、ロビンは目覚めた。
「う……」
ぼやけた視界は、全体的に暖色だった。むくりと上半身を起こす。
「ロビンっ!」
突然、温かいものが突進してきた。
「アニキ! アニキアニキアニキ!」
うるさいやつも飛びついてきた。角が体に刺さって痛い。
否が応でも、意識が覚醒する。数回瞬きをすれば、ロビンはすぐに現実へ戻れた。
「お前ら、どうしたんだよ……」
ロビンはヨーマンとマリアンを引きはがした。
ここはロビンたちの家だった。
おんぼろで住み慣れた、風通しの良いバラック小屋。寝慣れたぼろぼろベッド。
「だって、アニキ路上でぶっ倒れてたんだぜ!?」「よかった、ちゃんと起きて……!」
(おい、おれ首もげてたんだぞ)
ロビンは焦った。
「だ、誰が見つけた?」
「俺たち俺たち! 盗賊団で見つけてさあ、ヤバかったんだぜ!」
「え、血とか?」
「血なんかないぞ!? 札束に群がるチンピラですごかったの!」
ロビンは首飾りを換金して得た札束を、パンを入れた袋の下に隠していた。
「ちゃんと取り戻したから安心してくれよ!」
「いや、そりゃ別にいいけど」
「よくなくね!?」
「ねえ、ロビン、血ってなんのお話……?」
マリアンは真っ青な顔をしている。
「いや! そりゃ、悪い夢のお話だよ」
嘘は言っていなかった。
二人はロビンの元を離れた。朝飯を持ってきてくれるらしい。別段体に異常はないが、やりたいようにやらせることにした。
歪んだ四角の窓から外を見る。快晴。時計によると朝の十時。穏やかな日和だ。
(あれは夢だったのか?)
ラジオもこう言っている。
『エンド・グラウンド第17地区は晴れ模様。温かな日和の平和な1日に――』
サイレンが街を貫いた。
『緊急放送。マルアハが起動しました。緊急、緊急。マルアハが起動しました』
街の各所のスピーカーが咆哮する。
警報音。
『今すぐメトリオ方向へ避難してください。マルアハが――』
ロビンは家を飛び出した。
人の波、立ち並ぶ薄汚いバラックの向こう。
誰だってそれが見えた。だって、第17地区の高層の建物なんかたかが知れているし、何よりもそれは大きかった。ロビンは首が痛いくらいに見上げた。
『針鼠のマルアハ』と呼ばれている。
大きな丸い目を象ったものが顔の両側面についている。顔と言うよりも、それはまるでマスクのようだった。
『針鼠』の名は、体を覆う、大きさの異なる無数のトゲゆえ名付けられた。
地に着くほど長く大きい腕。長く伸びる尾がゆらゆらと揺れている。
煌々と輝く頭上の光輪。
「《アス・ポルタ》!」
ロビンの声は濁流に呑まれる。
大勢の悲鳴と叫びに惑う声。
「急いで!」「邪魔だ」「あの子がいない」「退け!」「押すなよ」「どうして」「マジで、ふざけんな!」
今ここが星で一番の我欲のるつぼだ。
ロビンの横を皆が走り去っていく。
地鳴りがする。あれが動き出した証拠。
荒れ狂う川のような人々の声たち。車のエンジン音。クラクション。鳴りやまないサイレン。大地を揺らす足音。最後にはあらゆる音が混じり、ごうごうと混沌のスープを煮やしていく。
だが、それは未だ鳴っている。唯一ロビンに聞こえているものがある。うるさいくらいに、己の心臓。
『……手に入れたら、自分が死ぬお宝だとしても?』
怪物を目の前にして、恐怖心でも湧いてくれるかと思っていた。人並に、恐ろしいと足がすくむことがあると。
だが、それを、上書きしうる衝動がある。
輪っかはきれいで、やっぱり欲しい。
手を固く握りしめた。
「"掴め"!」
黄金の手が遠く、二階のバラック屋根を掴んだ。大どろぼうはそれに引き寄せられて飛んでいく。
瞳孔の開いた金色の目は獲物を捉えている。向かうは天の御使い、狙うは頭上に浮かぶ《アス・ポルタ》だ。