第4話「始動」
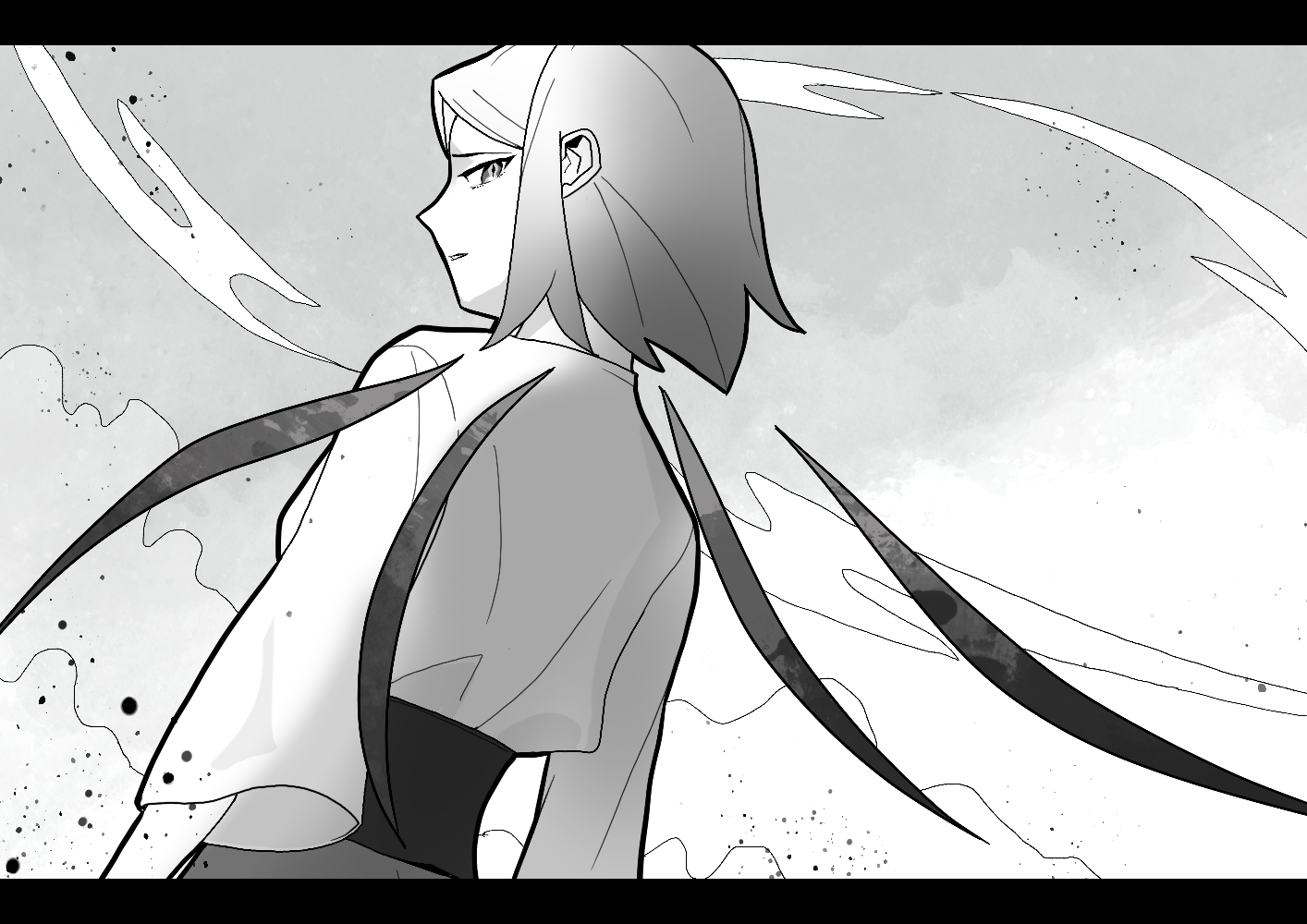
今から120年前、この星に7体の異生物が降り立った。
彼らは、それぞれの姿かたちをしていた。
背の高さが5階建てのマンション程度のもの、首都セント・グランドのオフィスビルほどの体長を持つもの。
仮面を顔として携えているもの、そもそも顔を持たぬもの。
しかし、7体共通してその体は白色をしていた。
穢れ一つない、目が痛くなるほどの純白。
皮膚に、青色の線が透けて見える。
膨大な魔力が、体のすみずみまで満ちている表れだった。ヒトなら静脈の管の色が浮いているようなもの。
彼らは、『マルアハ』と名付けられた。
7体の頭上に浮かぶ光輪は、たしかに、美しいものだった。恒星の輝きに似ていた。
しかし、あれは人類にとって恐怖の最たるものだった。
強力で惨い、星を滅ぼしうる兵器。
魔力を装填し、超火力の光線を放つ。
どんなに堅牢で、何千人もの魔術師が作り上げた防御術式であろうと貫く、白色の光を吐き出す。
光は照らすものすべてを消した。それを“浄化”と言い表すのは、マルアハを信仰するミツカイ教の信者たちであるが。
彼らに人類の構築した魔術式は通用しない。
侵攻の第一波において、世界人口の約5分の1が消滅したという。
◇
『ア ア ア ア ア ア ア』
怪獣は叫び、侵略を開始する。
その大きな腕で、気休めに建てられた防御壁を破壊した。
対マルアハ連合軍特殊作戦部隊司令塔――ナダイ・アルカディヴァ大佐は、シティ・メトリオの基地で、この一報を聞いた。
『と、言うわけで正式な通知が本部から下りた。すまないが大佐、人類のために死んでくれ』
通信は首都セント・グランドの快適な指令室から繋がれている。
既に特殊作戦部隊は出動の準備に取り掛かっていて、ナダイ本人も執務室で装備を身に着けている最中だった。忙しない中で、通信が否応なしにイヤホンから流れてくる。
「指令は正しく伝えるべきでしょう、大将殿。我々が本庁から命じられたのは、第04型の駆逐です」
『そうだな。できることなら、やってほしいけどね。いくら君であっても、他の誰であろうと、無理な話じゃないか。全く残念だ』
ナダイたち特殊部隊に与えられた任務は、針鼠のマルアハを討ち果たすすることであった。
実際のところ、マルアハを停止させることはできないから、市民が逃げる間の時間稼ぎを行う。
歴代の隊員もそうだった。生きて帰った者はいない。
生贄のようなものだ。
(何が残念だ、狐爺め)
ナダイは、使命感の元死んでやろうという気などさらさらなかった。
彼には野望を抱えていたし、この世界は自分のためだけにあると思っている。だからこそ、1から10まで馬鹿らしくて仕方がない。
『きみもこれで中将になれるぞ。今までの苦労が報われるじゃないか』
軍用コートに袖を通しつつ、話を無視する。
『“緑眼”の中将なんて、グランダリア本国では初かな? きみの夢も叶ったといえる……ナダイ君の素晴らしい人生に携わったことを、僕は光栄に思うよ』
「我々を処刑場に送った貴殿にしか言えない言葉ですな」
ポーチを腰から下げるために、プラスチックのバックルを填める。
そして、ダッフルバックを手に取って、執務室を出た。
『そうさ。僕もふんぞり返ってるだけじゃない。秩序を壊しかねない異物があるなら……必要最小限のコストで、処分しなければね。だけど、いろんな因縁を置いてさ……これはしょうがないことだよ。だれかがやらねばならない』
「ええ。貴殿も、いつか座る椅子でしょう」
廊下を歩きながら話す。
『いや? 僕はその前に天寿を全うする。先に死の国で待っていてくれたまえ』
「必ず生きて帰りましょう」
ナダイは一方的に通信を切った。これ以上話すことはない。
深く息を吸い、吐いた。
屋外に出れば、軍用ヘリコプターが回転翼を唸らせ、飛ぶ準備を済ませている。
隊員も皆そろっており、荷物を運び込んでいた。
強風の中で、ナダイを迎えに若手の隊員が駆け寄る。彼のダッフルバックを受け取った。
「ご一緒できて光栄です」
「逃亡は咎めん。なにせ、屈辱極まりない任務だ」
機内に乗り込む。
「大佐こそ、本当に良いんですか? てっぺんの椅子は、まだ取ってないでしょう」
赤色の粗末なベンチに腰かけて、背を壁に預けていた隊員のひとりが言った。
「逃げたと思われるのは癪だ」
シートベルトを填めた。
「新型の迎撃システムは、時間稼ぎになりますかね」
最後に乗り込んだ、若手の隊員がスライドドアを閉める。
エンド・グラウンドでは、市街地とマルアハとの間に、緩衝地帯が設けられている。
はたから見れば、それは居住区画のようであったが、もぬけの殻とされている。
この緩衝地帯に、迎撃システムと呼ばれる、マルアハの接近を感知し起動する、大仕掛けの魔術式が刻まれていた。
「ディカルド社の引き上げ型炎撃式と、クリキス家、ナマダ家合同の陥没拘束式だろ? 俺は30分に三十グラン」
「私は20分で五十」
浮かび上がる機体の中で、隊員の皆が、努めて普段通りに、明るくいようとしていた。
ナダイだけは何も取り繕わずに、自暴自棄を露にしている。
(なにもかも滅茶苦茶になればいい。中央にせよ、マルアハにせよ……他の思惑の中というのがいちばんに苛立たしい)
◇
そして、迎撃システムは12分で破られた。
ニュースは人々の喧噪の中を伝播していく。毒の霧が広がっていくような気持ちだった。
マルアハは緩衝地帯をじきに超えるという。
第17地区を駐屯地とする、対マルアハ連合軍グランダリア南東部隊は、市民の避難誘導を行っている。
だが、市民も軍人も、老若男女問わず、あらゆる人の顔は、多かれ少なかれ、恐怖というペンキで塗られていた。
人は、フェイク・アスの檻の中にいた。
フェイク・アスは地上のみならず、地下も覆っている結界で、マルアハの動きと連動し、囲う範囲を狭めていく。
触れれば、結界の魔力に身体を破壊される。
人類に許されたのは、大陸の内側へ、内側へと逃げることだけだった。
エンド・グラウンドとシティ・メトリオの間に、人工の壁が立ちふさがっているとしても。
「アニキ……」
ヨーマンとマリアンは、呆然と空を見つめていた。まだ、家の前を動けずにいる。
よりにもよって、ロビンは「ちょっと行ってくる」と言い残し、マルアハの元へ飛んでいってしまったのだ。
その姿は、もう見えない。
喧騒がヨーマンを急かす。ボーッとしている暇はない。
彼らのバラック屋根の家はエンド・グラウンドのより外側に位置していた。つまり、マルアハがここまで来るのに猶予はない。
「行くぞ!」
マリアンの腕を掴む。
「だ、だめだよ。ロビンを連れ戻さなきゃ」
目の焦点が合っていない。
ひと一倍臆病なマリアンは現実を受け入れられない。自己防衛的に拒んでいるようだった。
「先に逃げてろってことだよ! アニキなら大丈夫だって!!」
「でっでも」
「ンなら連れてっからなっ!」
ヨーマンはマリアンを俵担ぎで持ち上げる。
力には自信がある。角持ち――ガオエンの民の血だ。人並み以上の筋力はある。
(列車はあてにできねえ、どっかのトラックに乗り込んでも道路が動かないだろ。地下シェルター? 出てこれるか分かんねえじゃん!)
走った。
逃げるルートを頭の中で計算しながら、今は一歩でもここを離れなければならない。
「下ろしてっ!」
マリアンは足をばたつかせたが、ヨーマンにとってはあまりにも弱々しい抵抗だったから意味はない。
地上の通りは、どこも人と車で詰まっている。障害物をすり抜け、すり抜け、次にはそんな隙間はなくなっている。
「退け」「殺してやる」「ふざけんな」
人の悲鳴と怒号が入り混じり、動物の鳴声のようになって、世界に轟いていた。
マリアンは獣耳をぎゅっと畳んでいる。彼女の早鳴りの心臓の音が、肌から伝わってくる。
(ダメだ!)
ヨーマンはどうにかこうにか、藻掻いて人波をかき分け、押しのけ、一度横道に避難する。
裏通りを走る。行き止まりの道だったから、人はまだ少ない。
(上しかねえ、そこに盗賊団のヤツらもいるだろっ)
"上"というのは、ちびっ子盗賊団がこっそりと作り上げた秘密の道だった。
建物と建物の屋上に敷鉄板や適当な廃材を立て掛け、いざというときの逃げ道にしている。
「らあっ!」
ヨーマンはすぐそばにあった商業ビルの扉を蹴とばし、中に入った。カギなど勿論かかっていない。
屋内に人気はなかった。つけっぱなしのテレビの音が、無機質に流れている。
「お、下ろしてよお」
「うるせうるせうるせ!」
マリアンを走らせるより運んだ方が断然早い。
階段をどたどたと駆けあがる。
終点、屋上行きのスチール製のドアは、ラッチボルトが壊れていていつだって開いている。
ヨーマンは片足で蹴飛ばした。
こんな日に限って、嫌に快晴だった。昼の日差しはからっとしている。
「あ……?」
四階建ての屋上には先客がいた。
「さっきの、やっぱりボビンくんですよ!」
「俺はよく見えん……」
男女の二人組が、空を見回し何かを探している。
つま先立ちで遠くを見やる紫髪の若い女。
柵に身を預け、煙草を吸っている中年に差し掛かったあたりの男。
階下の地上では、あんなにも人が押し合いへし合い、恐怖の大嵐が吹きすさんでいるというのに、二人はどこ吹く風と言わんばかりに落ち着いている。
「バーカ! イチャこいてんじゃねえっ!!」
ヨーマンは八つ当たりをした。
「いっ」
女は目を丸くする。
「元気だねえ」
男がこれだけ言ったから、余計ヨーマンはムカムカした。
ヨーマンはマリアンをようやっと下ろしてやる。
「気持ち悪い……」
男女に意識を割いている余裕などない。
付近をがさごそと漁り、室外機の隅っこに隠しておいたロープを取り出した。
下ろした途端、マリアンはふらふらと歩き出し、きょろきょろ辺りを見回している。
「マリアン! フラフラすんな!」
「わ、分かってる。で、でも、ロビンがいる、気がして」
(ウソだ!)
辛抱溜まらず、ヨーマンはマリアンを捕まえた。頬を両手で挟んで、強引に自分の顔を見させる。
「いいか! アニキを待ってちゃ俺たちが死ぬんだ! どうせアニキなんてどこでもピンピンしてんだから、マルアハに踏まれたって、ビーム喰らったって、大丈夫!! 無敵で、最強の、大どろぼう!! だから!!」
「うん、わ、分かってるけ」
「逃げるんだよーーっ!!」
「わ、分かった、分かったよぅ」
ヨーマンはマリアンの頬っぺたを解き放った。
「お前大丈夫か」
「ケンカしちゃダメですよ」
「うるせーーーーっっ!!! なんだお前らっ!!」
(くそ、大丈夫、大丈夫なんだ。絶対に……!!)
手早く自分の胴にロープを巻く。頭がおかしいアベックに構っている暇はない。
マリアンは変わらず、辺りを落ち着きなく見回していた。瞳がゆらゆらと動いている。
彼女の弱気が伝染して、ヨーマンだって今にもへたり込んで仕舞いそうだった。心臓が痛いくらいに鳴っている。怖くてたまらない、死ぬのは嫌だ。
地上で逃げる人の波が、大雨の後の川のようだった。
遠くで、マルアハの足音が聞こえた。サイレンが鳴りやまない。
同じ要領でロープのもう一方の側をマリアンに巻いた。高所で細い足場を渡るから、簡素ではあるが命綱だ。
ヨーマンは頬を両手で挟んで何度も叩く。自分の中の恐怖に出ていけ、出ていけと念じた。
マリアンはまだ、ロビンを探している。
なにせ、さっき感じ取ったのだ。明確に、ではなく微かな残り香をかぎ取る、というレベルではあるが。
彼女は、魔力を感知するのが得意だったから。
「あ」
マリアンは振り返った。マルアハのいる方向。
奇妙なリズムの魔力を感じ取る。我の強い魔力。唯一無二の。
瞳に光が灯った。
「ロビンだっ!!!」
マリアンが空を指差した。
きらきら光る五芒星だった。
真昼間でも、輝きをまき散らす。紛うことなき、黄金色の手のひら。
真っ赤なスカーフが見えた。
「アニキだっ!!!」
この時ばかりはヨーマンも、マリアンと二人してフェンスに駆け寄った。
マルアハを正面に見据え、ヨーマンたちから見てロビンはその東側にいるようだった。
「アニキ、マジで輪っか盗りに行きやがったっ!!」
「連れ戻さなきゃ!! 死んじゃうよ!!」
「アニキーーーーーっっっ!!!!」
ヨーマンは精一杯の大声で叫んだ。
聞こえたのか? 聞こえなかったのか? あの小さくなっていく米粒は、振り返るそぶりも見せない。
巨大な怪物の大影に、小さな光が飛び込んでいく。
(アニキはマジで悪魔に魂を売ったんだ。だから、地獄に落ちる……)
ぼきっと、ヨーマンの心の中でなにかが折れる音がした。
「絶対、絶対ムリだってええええ!!!」
ヨーマンはへたり込み、泣き出した。
頼りの兄貴は死んでしまうに決まっている。あの大きな怪物に潰されて終わりだ。
あんな大きな怪物を、子どもがどうにかできるはずがない。
「ヨーマン、ロビンが行っちゃうよ!!」
「うわああああムリだああああああ」
マリアンはロープを引っ張った。しかし、号泣するヨーマンは一歩も動かない。
もたもたしているうちに、星は遠くに消えてしまった。
「ロ、ロビン……」
マリアンも座り込んだ。そして、しくしくと泣き出す。
遠くでズズンと、音が大気を揺らす。
爆撃機が風を裂いて、マルアハに向かって行った。キイン、という音が耳の中で残響している。
「おい、追いかけるぞ」
「ごめんなさい、先に行ってて」
女はフェンスから離れる。男はふう、と息を吐いた。
「あの子、ロビンって言うんですね」
ふたりのそばでしゃがみ込んだ。
マリアンは顔を上げる。
彼女は――眉を八の字にしている。そういう顔つきらしかった。
アカツキ人らしい細い目。
セミロングの髪と、その下から伸びる長い、四本の髪束が印象に残る。清潔感のある格好。
「そうだ、大どろぼうロビン!! 星いちばんのバカバカッバカ野郎だっ!!」
ヨーマンは顔中の液体をまき散らして突っかかる。
「あなたの友だち?」
マリアンの目からぼろぼろと涙が落ちる。
「か、家族です。たっ助けてください、ロビンが死んじゃう」
マリアンは女に縋った。
女は瞼をわずかに上げる。振り払うこともなく、そのままにしている。
「……そうなんだ。だったら」
マリアンの潤んで歪んだ視界に、女が映っている。
逆光で影に包まれた顔で、赤色の目が不吉に浮かび上がっている。
「離れ離れはいやですよね」
女はマリアンを抱きしめた。
柔らかい体にひとの温み。淡い柔軟剤の匂いがした。花の匂い。
同時に、マリアンは違和感を覚える。
(――この人も、ロビンと同じ)
「おい、坊主も、あとちょっと頑張れ」
男も、ヨーマンの肩を揺すってやった。
「希望はある。マルアハを倒せるかもってのが、少なくとも三人いるんだ。本当に」
「ウソだあああ」
「本当本当」
「へっ!! じゃあどこのだれが倒せっ――」
第六感が警鐘を鳴らす。見えない刃の切っ先。
殺意。
「伏せて」
男は二人の子どもを抱え込み、その身を伏せた。
「ぐえっ」
ボロい、黄ばんだビルの向こう側。
マルアハが地に這うような姿勢で、動きを止めていた
体表で、針が煙を噴き出している。
針鼠のマルアハの体を覆う、円錐状の針――大きさはまばらながら、ミサイルじみた形をしている。
それは、見た目通りの働きをした。
「ア ア アア ア ア アア」
拍手のようなまばらさで、次々に発射音が轟いた。煙の軌道は、四方に飛び散る。
"針"は進路上にあるビルを貫き、爆発した。
(来る)
切り開いた道を、後続の数十本の棘が、こちらへ襲い掛かる。
女は三人の矢面に立っていた。瞼を閉じる。
両腕を軽く広げる。細い腕。
「“見て”」
目を開けた。赤色の瞳。
内から魔力があふれ出す。
マリアンは地面に縋ったまま、その光景を見上げた。
(あれ、髪じゃない)
陽光に照らされ、硬質な物体のきらめきを返す。
しかし、鞭のようにしなる。
女の四本の髪束、それは刃だった。
赤く、色を変える刃。
四本は、それぞれが別の生物であるように動いた。飛来する針へ向かって行く。
獲物を狩る蛇のようであった。
着弾する前に、ミサイルを叩き切る。貫く、切り刻む。漏らさずに。
ひとつの獲物を喰らったら次へ、どう猛に襲い掛かる。
女の細い指が、最小限の動きで指示を出している。
「"見て"」
落ちてくる残骸をも切った。凶暴な刃は、執拗に獲物を刻んだ。
死骸を貪るピラニアのようだった。
女は下唇を噛む。
極度の集中と、大量の魔力使用で、目と頭が痛む。目が熱い。
女の表情は、三人には見えない。
空に、次々と爆炎が生まれる。まるで花火のようであった。
爆炎にさらなる針が飛び込んできても、次の瞬間には破壊されていた。
巻きあがる黒色の煙。
「お姉さんっ!!」
煙幕を切り裂いて、殊更大きな針が落ちてくる。
「っ!」
刮目し、男は立ち上がろうとする。
「大丈夫」
手を交差する。
その合図で、四本の刃が合わさった。より大きく、太い刃を形成する。
女は荒い息を押さえ、努めて、笑いかける。
「なんとかします、だから、お願いだから、私を、見ないで、くださいね」
そして、彼女は三人に聞こえないように、スペルを呟いた。
「お姉さ――」
男が、マリアンの視界を手で覆った。
上空で、蛇は、殺意の円錐に潜り込む。
赤色のヒビが走る。
円錐は、不思議とその場で立ち止まった。
(見て、私を、私を、私を、私を、だ、だめだ、ダメだ)
針の内側で、次々と刃は枝分かれをしていた。
毛細血管のように細かく際限なく、しかし、確実に内側から、“体”を破壊していく。
刃が、物体を切り進んでいくその感触が、頭に伝わってきている。女は歯を食いしばる。
――殊更大きい、爆発が起こった。
切り残しはなかった。
女の、白いブラウスの袖が風に吹かれている。
刃は、煙の中から、平然として女の元へ戻ってきた。
しゅるしゅると髪の下に収まる。
男はマリアンの瞼から手を離した。
「すまんね」
マリアンは瞬きをする。
しばらくしてから、女はふう、と息を吐き、振り返った。
赤色の瞳。縦長の瞳孔。
「怪我はありませんか?」
マリアンは、全身の毛が逆立つような気持ちだった。
蛇に睨まれた蛙。
この目で見ていなくても、暗闇の世界で、動き回っている魔力の流れは感じ取っていた。
彼女は紛れもない異常者だ。破壊に特化した力。
魔術は、その使い手の色を反映する。
「助かった」
男は返事をした。
ヨーマンも顔を上げる。久々の現実世界だった。
「マ、マリアン。何があったんだよ」
脅威であった針の雨はどこかへ消え去っている。
「あなたは、だれですか?」
マリアンは女に聞いた。
彼女は一度、目を逸らした。
一寸逡巡してから答える。
「私は……ヒガン。ヒガン・シエ。見、見ちゃいましたよね、あの――」
「ありがとう、ヒガンさん」
マリアンは言った。
二人は去って行った。階段を降りて、地上に戻る。
紛れもなく、終末へ近い方向へ。彼らは、大どろぼうのいる方へ行くのだ。
地上で、ざわめきが聞こえた。彼女の刃で、命を救われた人たち。